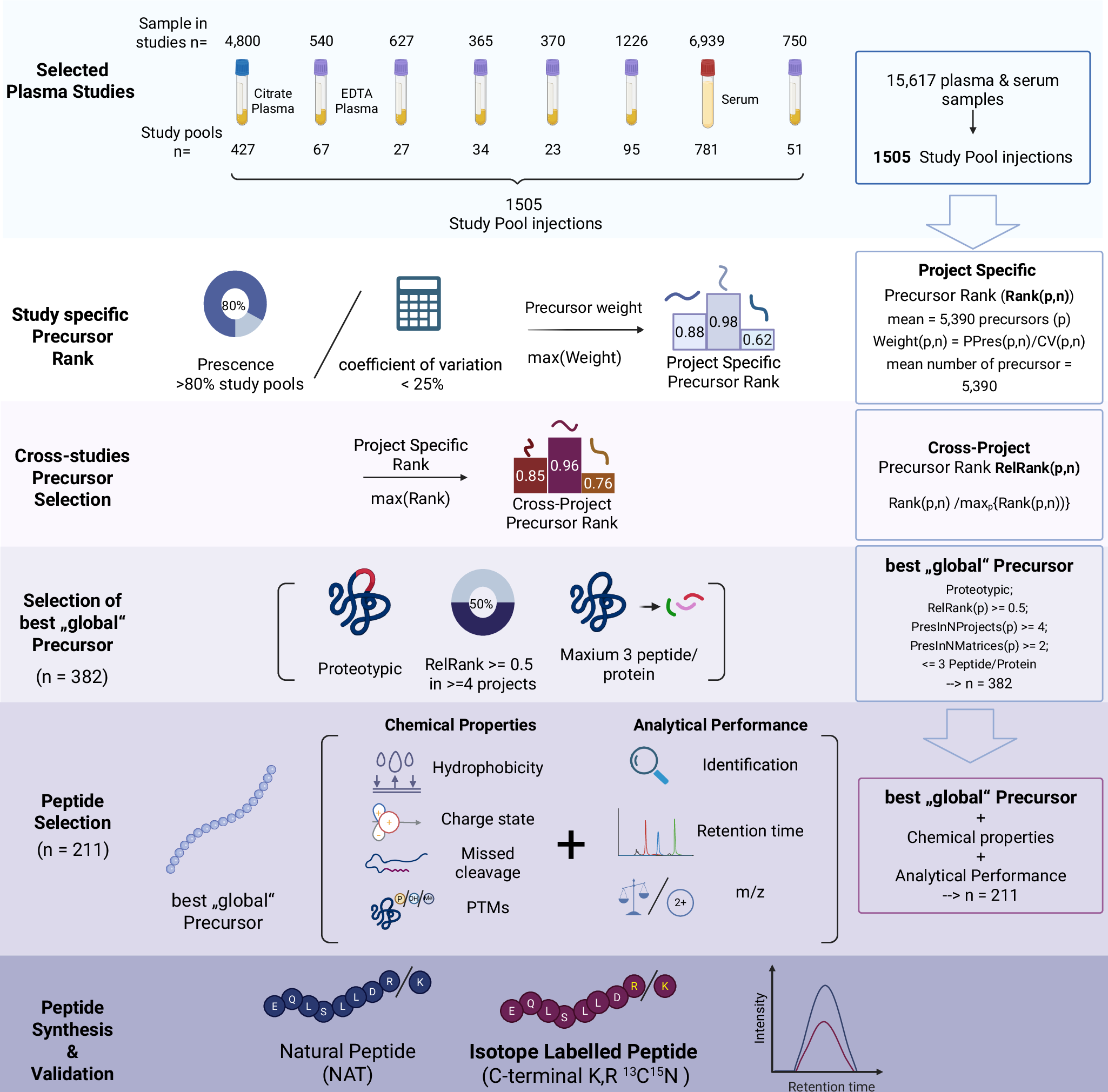今回紹介するのは、上向き圧カタパルト型レーザー微小切除(LCM)とLC–MS/MSによる空間プロテオミクスのための新しい前処理ワークフローMR-SP2(Microreactor-based Sample Preparation for Spatial Proteomics)です。FFPEマウス腎臓で定義領域を狙ってLCM回収し、マイクロリアクター内でのワンポット溶液内処理により吸着ロスを最小化、さらにEvotipディスポーザブルプレカラムを用いたピペット操作不要の移送を組み込むことで、回収から前処理、導入までを一貫化しています(Evosep本体の使用有無は抄録では不明)。
結果として、約22細胞相当の50,000 μm3ではタンパク質同定数が3,381 ± 80にわずかに向上(対照3,174 ± 59)し、入力が少ないほど優位性が拡大しました。5–6細胞相当の12,500 μm3では1,145 ± 188(対照302 ± 126)、1–2細胞相当の3,125 μm3では695 ± 112(対照206 ± 51)と、少数細胞FFPE試料で同定深度を最大約3倍に改善。MR-SP2は上向き圧カタパルト型LCMに適合した堅牢な前処理を提供し、単一細胞スケールの空間プロテオミクスにおける同定率と再現性の向上に寄与します。